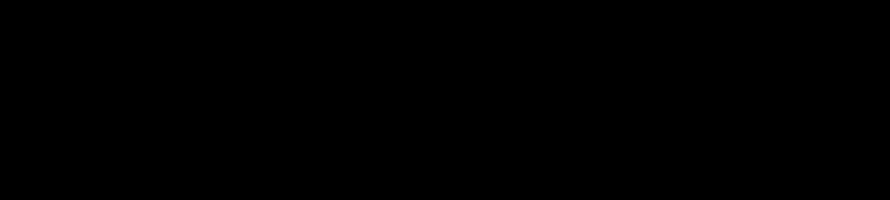
フォンタネッレ洞窟教会
納骨堂

容赦なく照りつける強烈な日差しに痛みを覚えながら、雲一つない真っ青な空の下、都市の中心から少し外れた一角を、陽気で軽快なナポリの友人たちと歩く。
古くからの地元の人々が変わらずに暮らすこの一帯は、まるで東南アジアの小都市にでも迷い込んでしまったかの様な錯覚を抱かせる程、それまでに観貯めたイタリアの街並とは一線を描く特有の雰囲気を漂わせていた。
地面に敷かれた石畳が返す熱気に水分を奪われ、注ぐ日差しに視界を奪われながら、ようやく目的の洞窟へと辿り着くと、そこは余りにも自然にそれまで歩んで来た街並に溶け込んでいて。
劇的な温度差と明暗差だけが、そこが特別な意味を持った空間である事を静かに強調していた。
歴史を遡る事300年余り、当時、絶大な力を持っていた教会で、貧しい人々はその信仰心に関わらず葬儀をあげることなどできなかった。
ここはそんな人々が共同で納められ、今も多くの地元の人々が祈りを捧げに足を運ぶ歴史的な場所で。
南イタリアの持つ陽気で開放的な印象とは対照的に、陰鬱で閉じた空間と歴史とを静かに今に伝える場所。
入口から届く青白い光が洞窟の深さを物語り。
かつて人々の手によって掘られた岩肌がその奥行きを誇張する。
外部の日差しなど嘘だったかのように、流れる空気はすっかり熱を失い。
そんなひんやりとした空気と骨々の間を縫う様に内部へと歩を進める。
ふと、木製の棺が横たわる。
全身を留め、そこに眠る事が出来たのは、かつて小さな身分を持った人たちで。
そこに書かれた文字が意味を留め、時間の経過が意味を奪う。
暗闇は一歩一歩確実にその濃さを増し。
流れる空気が湿り気を含み始めると。
やがて浮かぶ美しい木製の像、静かに十字を切った。
入り組んだ道、それでも変わらず在るのは左右を満たす膨大な量の頭蓋骨。
それら名を持たぬ、富を持たぬ人々に、この土地の人々は尊敬を払う。
木製の小さな棺を造り。
掃除をし。花を供え。祈りの道具を飾り。
祈り。話し。願いを掛ける。
これらはそんな人々の崇高の形。
そしてそんな骨々の合間、教会の印も少しだけその姿を見せる。
どこまでも続く暗闇を進むと、そこに不自然に落ちる自然の光。
その十字の麓には、名を持たない頭蓋骨たちが積み上げられていて。
人々の祈りの上にも、平等に時間は積もる。
あまりの情景に息を飲み。
しばらく言葉を忘れてその場所に立ち尽くす。
やがてそこから伸びる暗闇の中に戻ると、そこに在ったのは時に美しくすら思える人間の崇高信。
時間を忘れて歩き回り、やがて冷えた暗闇から光の元へと戻る。
外、照る日差しは変わらずに痛く。
遠く、どこかでカラスが鳴いていた。
























































